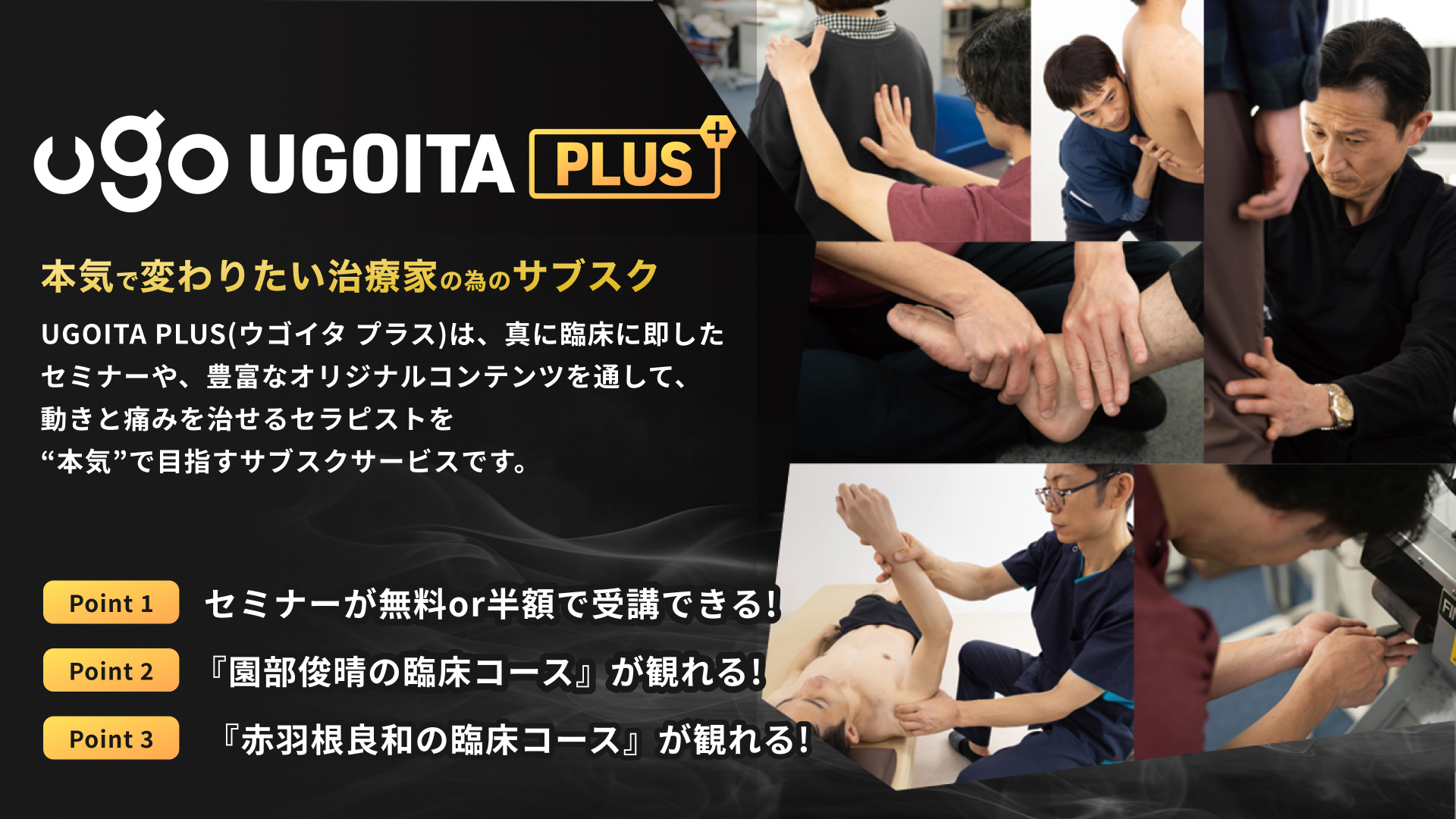【講義内容】
「拘縮」と聞くと、四肢が固まった状態を想像する方が多いかもしれません。実際、多くのセラピストは「拘縮」という言葉から、関節の可動性が著しく低下し、硬直した状態を思い浮かべるでしょう。しかし、私が定義する「拘縮」は、これに限ったものではありません。軽度の可動域制限や、組織間の滑走性の低下なども含めて、「拘縮」と呼んでいます。
一般的な拘縮の治療では、硬くなった組織を伸ばしたり、ストレッチや可動域エクササイズを行いますが、これらの方法は過度な伸張や圧迫を引き起こし、痛みを増強させるリスクがあります。その結果、関節可動域の改善が進まないケースも少なくありません。
私が20年以上の臨床経験で得た知見によれば、拘縮の改善は運動器疾患の治療において極めて重要です。拘縮が改善されると、多くの場合、その場で痛みが緩和され、同時に関節の機能も向上します。したがって、この章では、拘縮の概念とその治療の重要性について詳しく解説します。
拘縮とは、「関節周辺の軟部組織が伸張性・滑走性・柔軟性を失い、正常な関節運動から逸脱し、過度な負荷が生じ、疼痛や可動域制限を引き起こす状態」を指します。例えば、肩関節後方の組織に拘縮がある場合、屈曲の最終域に到達する前に緊張が高まり、関節軸が前方に変位し、肩関節前方の組織に圧縮力がかかることで痛みが発生します。このように、拘縮は関節の求心性を乱し、正常な運動軌道から逸脱させることで疼痛を引き起こします。
このような理由から、セラピストが行う拘縮治療では、軟部組織の伸張性・滑走性・柔軟性を改善し、正常な関節運動軸を整えることが重要です。
本章では、皮膚、筋・筋膜、靱帯、関節包、脂肪体、滑液包、神経など、臨床で拘縮を生じやすい組織の特徴や評価方法、治療方法について、実際の動画を用いて紹介します。
【カリキュラムの特徴】
①拘縮とは?
②なぜ拘縮が生じると痛みが生じるのか?
③皮膚性拘縮とは?評価と治療
④Fascia拘縮とは?評価と治療
⑤筋性拘縮とは?評価と治療
⑥靭帯・関節包拘縮とは?評価と治療
⑦脂肪体拘縮とは?評価と治療