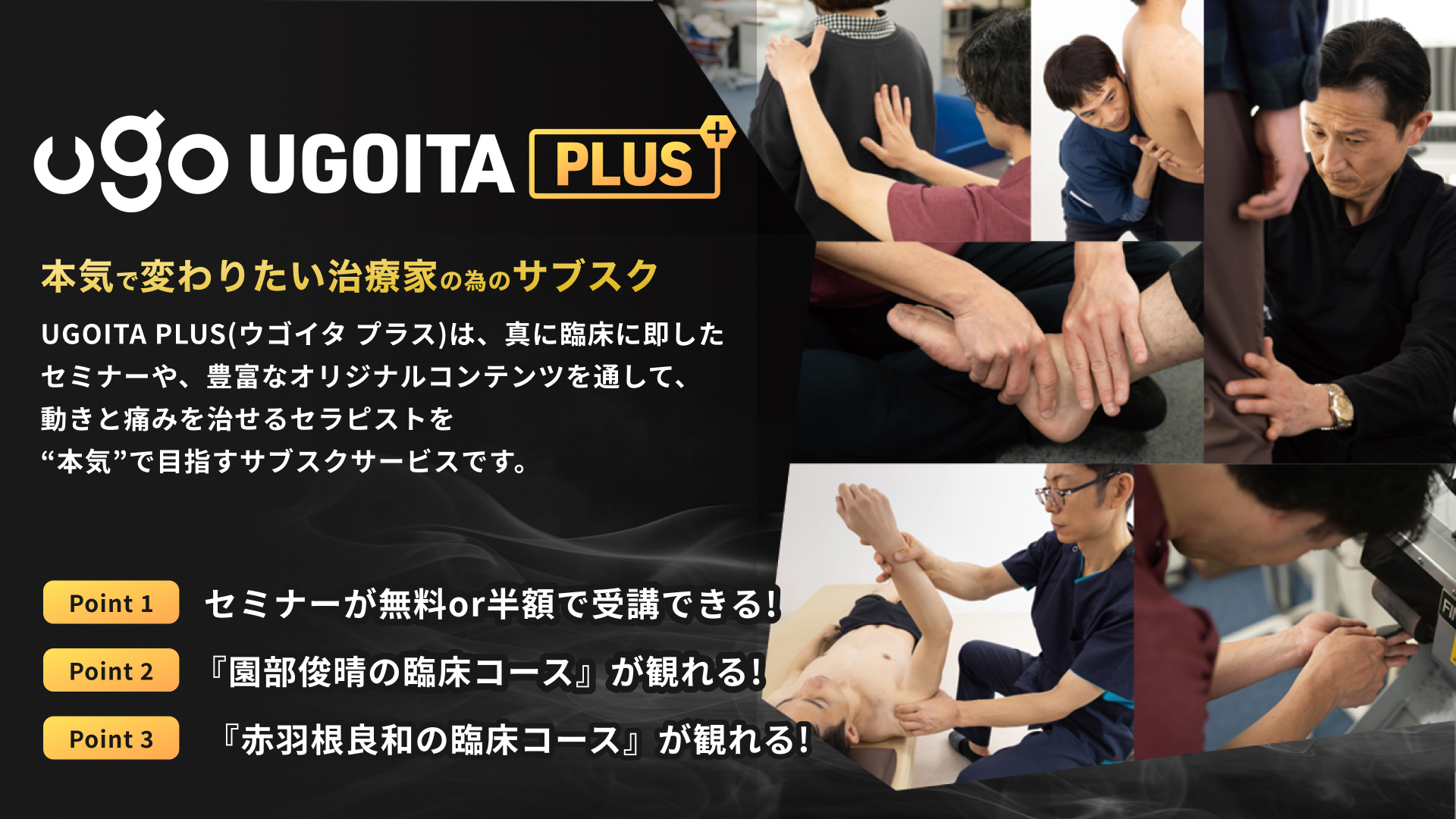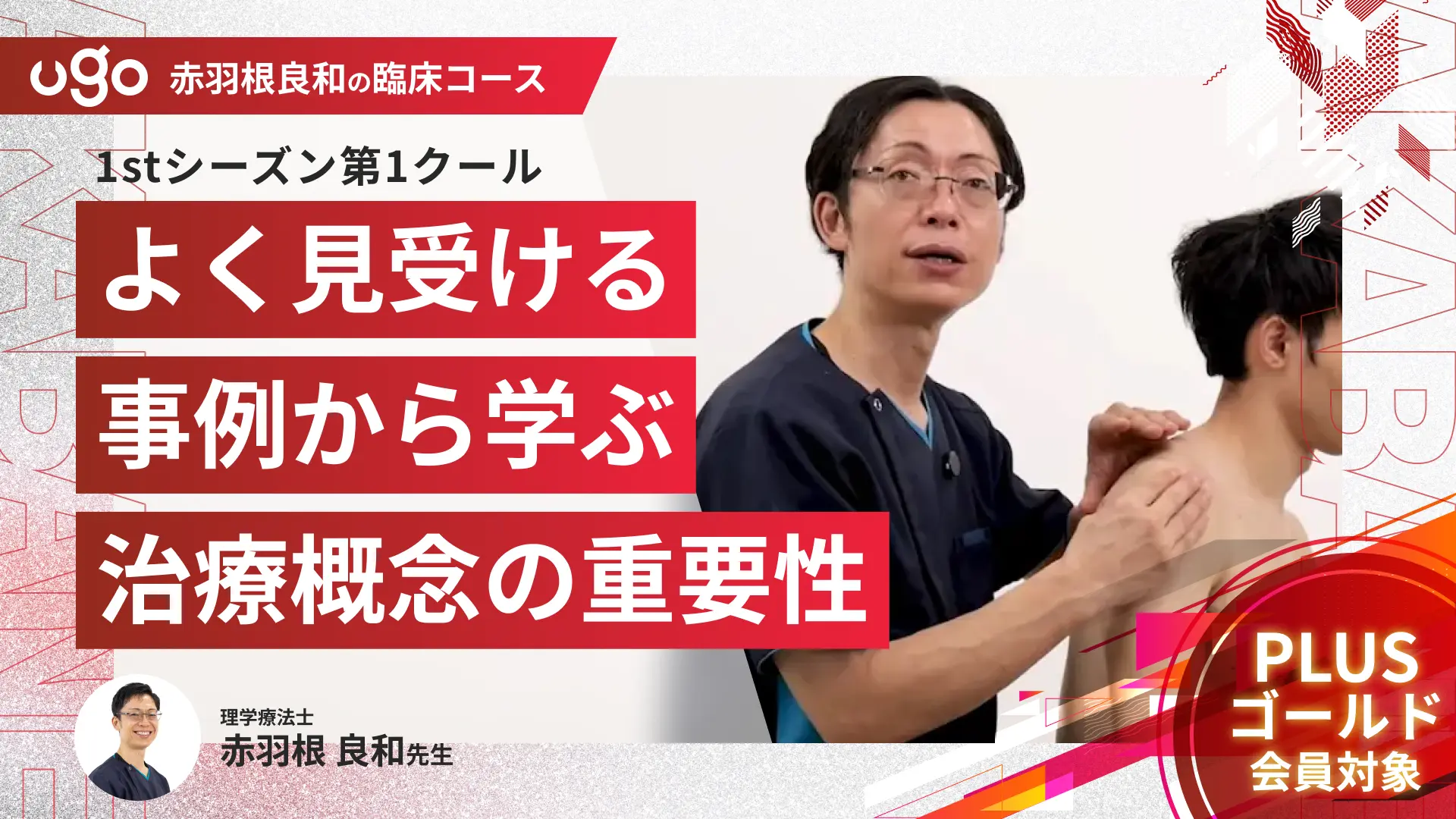【講義内容】
運動器疾患の分野において、患者が医療施設を訪れる主な理由のほとんどは「痛み」です。たとえば、変形性膝関節症や変形性股関節症のような疾患では、変形が進行したこと自体よりも「痛み」を訴えて来院する方がほとんどです。同様に、肩関節疾患においても、肩関節の変形が進行したから来院するのではなく、肩関節の痛みで訪問することがほとんどです。
このことから、私たち医療者はまず「痛み」を改善させるための知識と技術を習得することが不可欠です。しかし、「痛み」を取り除くためには、単に医療知識を増やすだけでは十分ではありません。豊富な知識を持つ教育者であっても、実際に「痛み」を抱える患者に対して即座に効果的な治療を施すことは容易ではないからです。そのため、「痛み」を軽減するには、運動器医療の知識に加え、臨床に基づく治療アプローチが不可欠と考えられます。
したがって、知識と治療アプローチの両方を身につけ、実践を通じて継続的に向上させることが、「痛み」を和らげるセラピストとして成長するための確実なプロセスであると言えるでしょう。
この章では、セラピストが誤解しやすい治療手順について解説し、治療のprimary(一次)とsecondary(二次)の違いについても説明します。痛みを呈する患者に対して、まず「痛みの原因組織」を見つけることが重要です。この「原因組織」と「その組織に加わる直接的な負荷」を痛みのPrimaryと呼びます。一方で、「Primaryの状態を悪化させる因子」を痛みのSecondaryと定義します。痛みを改善するためには、このPrimaryとSecondaryの2つを明確に区分し、適切な治療を行うことが不可欠です。
しかし、臨床現場では、この区分が曖昧になることが多く、痛みの原因を見誤ることがあります。例えば、Hip-Spine Syndromeでは、股関節の屈曲拘縮が腰椎に負荷をかけ、腰痛を引き起こします。この場合、Primaryは腰椎の組織、Secondaryは股関節の屈曲拘縮です。
このように、PrimaryとSecondaryが明確に分離されている場合、臨床推論は容易ですが、隣接しているケースでは区分が曖昧になりやすいです。 痛みのPrimaryを見つけるためには、第3水準の評価が有効です。これは、徒手的な操作を加えて痛みを消失または緩和させることで、原因組織を特定する手法です。エコーガイド下での注射技術もこの評価法に基づいており、原因組織に対する効果を確認する手段として有用です。たとえ痛みが再燃しても、最初の消失が重要な情報となります。 このように、痛みのPrimaryとSecondaryの概念を理解し、第3水準の評価技術を習得することで、治療の精度を高めることができます。この2つの概念を深く理解すると、1−2の拘縮が痛みに与える影響についても理解が深まります。次の項目では「拘縮と痛みの関係」について詳しく説明します。
【本講座から学べること】
①これまでの運動器診療の現状
②現在の運動器診療と私たちが目指すべき運動器診療
③何が痛いのかを明確にするための方法
④疼痛発痛源評価
⑤primaryとsecondaryの概念を理解する